

いま、子どもから青年、親世代から高齢者に至るまでの多世代が、
一人ひとりの 「こども」 に寄り添い、子どもの本質を見つめ「こどもを学ぶ社会」が求められています。
日本こども成育協会は、次代を担う子ども(0 歳~ 10 歳ごろ)の成長と発達を理解し、子ども一人ひとりが、自立した個人としてひとしく健やかに育つことができるよう、
最適な成育環境(人間・空間・時間・情報システム)の構築を目指します。
子どもの成育環境にあるモノやコトを創り出すことを「こども成育デザイン」と呼んでいます。
「育つ子ども」と「育てる大人」の幸福に配慮した「こども成育デザイン」が、
あらゆる産業やコミュニティにおいて、実現するように本協会は、発達心理学および子どもの成育に関する
諸科学の知見に基づいて製品やサービスの開発、人材育成の支援を行います。
現在、本協会では以下の「 3 つの視点」から子どもを学び、成育環境を構築する事業を行っています。

クラウドファンディングのCAMPFIRE for social good で183%達成したパパ待望の子育てスキル講座がいよいよ始動します!
スマホで、PCで、お好きな時間に講義動画視聴をすることで「うちの子専属トレーナー」資格が取得できます。
パパ育児の基礎篇+子どもがパパを好きなる専門分野2種「ワイルドベビートレーナー」と「はみがきトレーナー」がオンデマンドで学べます。
協会からは、理事の沢井佳子先生と協会アンバサダーの宗田香織さんが講師として参加しています。
パイロット版視聴の先輩パパ達が「もっと早く知りたかった!」と、現役乳幼児パパに激推しする講座。
ぜひ、周りのプレパパや絶賛子育て中のパパたちにもお知らせください。
◆受講申し込みページ
https://kodomoseiiku01.peatix.com/

クラウドファンディングのCAMPFIRE for social good で183%達成したパパ待望の子育てスキル講座がいよいよ始動します!
スマホで、PCで、お好きな時間に講義動画視聴をすることで「うちの子専属トレーナー」資格が取得できます。
パパ育児の基礎篇+子どもがパパを好きなる専門分野2種「ワイルドベビートレーナー」と「はみがきトレーナー」がオンデマンドで学べます。
協会からは、理事の沢井佳子先生と協会アンバサダーの宗田香織さんが講師として参加しています。
パイロット版視聴の先輩パパ達が「もっと早く知りたかった!」と、現役乳幼児パパに激推しする講座。
ぜひ、周りのプレパパや絶賛子育て中のパパたちにもお知らせください。
◆受講申し込みページ
https://kodomoseiiku01.peatix.com/

「子どもの才能を発見し、伸ばすにはどうしたらよいか?」というテーマで
協会理事の沢井佳子先生がお笑い芸人のチャンカワイさんと対談した記事が
KIDSKI STYLE(キズキスタイル)さんで公開されました。
ぜひご覧ください。
前編:才能をつくるのは多様な経験から?
認知発達から紐解く、子どもの才能開花を解説!
https://kidski.kidsna.com/kidski-style-article/0000000048
後編:子どもは親の感情を観察している?
子育ての重要なキーワードは「子どもと一緒に〇〇」
https://kidski.kidsna.com/kidski-style-article/0000000049

安心して子育てできる家づくりについて、子どもの認知発達の知見に基づいて
沢井佳子先生が、また、子どもの発達に応じた安全について羽富孝が監修しました。
ぜひご一読ください。
子どもの成長と発達にとっていい家、子育てしやすい家とは? 一条工務店様
https://www.ichijo.co.jp/lp/childcare/
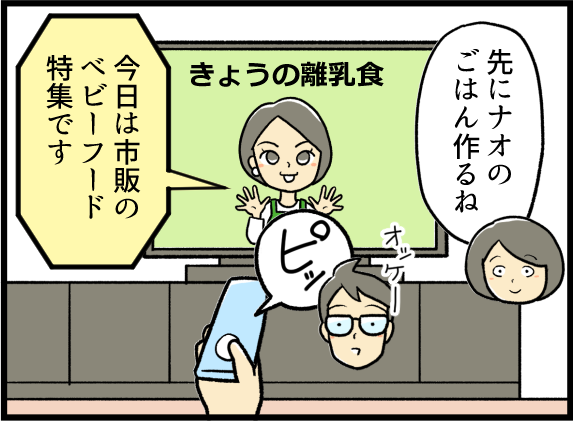
当協会メディアパートナーの一つである『こそだてDAYS』さんで、こども成育〈食専科〉講座 ディレクターであり管理栄養士の隅弘子さんと協会が記事の監修をしています。
今回のテーマは『ベビーフード』です。
家事育児の負担軽減、外出時の食事、そして災害などの緊急時の食事にも役立つベビーフートについて、その種類やメリット、デメリットなどをご紹介しています。
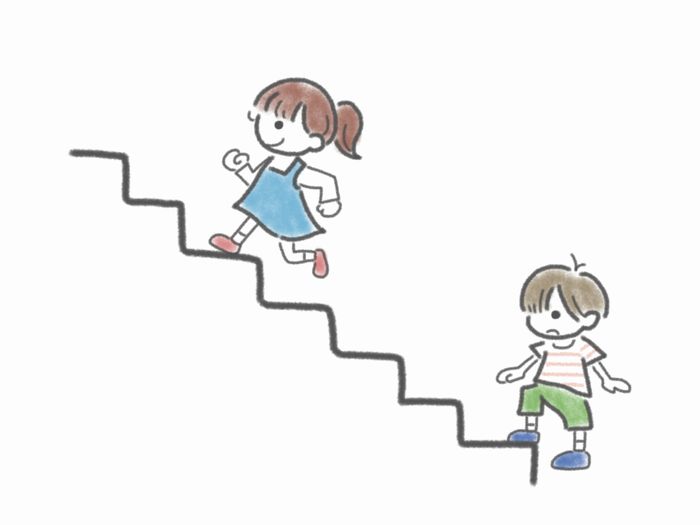
「育児の現場でさらにパパが活躍してほしい!」
そんな想いを込めて開発をした「うちの子専属トレーナー」認定講座。
今回は、前回に引き続きパパ育児の基礎篇となる『こどもの発達の基礎』を
ご紹介します!
前回の記事はこちら▼
「散歩」は夫婦のよりよい関係づくりの特効薬!? うちの子専属トレーナー パパの基礎篇
『こどもの発達の基礎』の講師は、当協会理事の沢井佳子先生です。
「パパしるべ」の編集長であり、同じく「パパの基礎篇」の講師を担当する
杉山錠士さんをナビゲーターに、幼児期の発達心理のエッセンスをぎゅっと凝縮してお届けしています。
本講座で特にフューチャーしているのは、「子どもは論理的に発達する」という点。
ポイントは
☑ もともとインストールされたプログラムが順序どおり出現する
☑ 曲線ではなく、ある日突然(のように見えたり、感じる)次の段階に進む
ということです。
そして、「発達スケール」についてもご紹介しています。
この「発達スケール」は、『こども成育講座』や沢井佳子先生の編著『子育て大全』でも
取り上げていますが、子どもの発達の順序を多領域における具体的な行動で示した
一覧、マップのような図表です。
「うちの子専属トレーナー」講座をすでに受講いただいたパパたちにも
この「発達スケール」は、子どもの発達の全貌を知ることができると、大変好評でした。
また、お子さんの発達を見るときに、どうしても「発語」など、
親の関心のある分野ばかりに目がいきがちですが
言語だけでなく、社会性や、論理性・数量の理解、自然への関心や知識などを含め
総合的な視点で観察することが大事であるということも解説しています。
さらに、「パパが子どもとやり取りするときの3つのポイント」や
子どもと接するときにやってみるとよいことなど
知識を得るだけでなく、講義を見たらすぐに実行に移せるような工夫もしています。
ぜひ、プレパパや子育てに奮闘中のたくさんのパパたちに届くよう
応援をよろしくお願いいたします!

昨年末よりプロジェクトがスタートし、春のクラウドファンディングを経て
今秋に本格的に始動した「うちの子専属トレーナー」認定講座。
先月は、選択科目の一つである「うちの子専属「ワイルドベビー」トレーナー」認定講座を
ご紹介しました。
新聞紙やタオル、ティッシュペーパーも立派なトレーニングマシン!?
本日は、基礎編としてご提供している2科目から「パパの基礎」に注目してお伝えします!
講師は、日本こども成育協会のメディアパートナーであるパパ向け子育て情報サイト
『パパしるべ』の編集長であり、「うちの子専属トレーナー」の開発仲間である杉山錠士さんです。
「育児&夫婦コミュニケーションの基本的な心構え」というテーマで
アドラー心理学をはじめとする多様な研究や調査の結果から
パパが心得ておくと、育児がさらに楽しく、豊かな経験になるような知見をお伝えしています。
皆さんは、一日あたり話す言葉の数に男女差があることをご存じでしょうか?
そうした差があることを理解していれば、育児に奮闘しているママの話の聞き手になることが
どれだけママの心理的なサポートになるかが分かると杉山さんは解説します。
また、ちょっとした言葉の使い方を変化させることで、コミュニケーションがスムーズになる
コツなど、夫婦間のみならず、親子間、あるいは職場での円滑なコミュニケーションにも
役立つような情報が詰まっています。
また、「散歩」という行動が夫婦関係によい効果があるという、とても興味深い情報も!
横並びで同じ方向を向き、雑談をしながら歩調を互いに合わせて歩くという形から
入ることで、心理的な歩み寄りにもよい影響をもたらすそうです。
このように、「うちの子専属トレーナー」基礎A:パパの基礎は、
杉山さんご自身の経験も踏まえ、「パパの心構え」として即実践できる情報満載の
協会も自信をもっておすすめする講義内容となっています!

日本こども成育協会 理事の大塚千夏子です。
私たちが賛助会員として参加している学会のひとつに日本子ども学会があります。
先日、年に1度の学術会議が青森の認定こども園八戸文化幼稚園で開催されました。
私は2日間のプログラムにオンラインで参加しました。
1日目の基調講演は、絵本制作の編集者のお話しでした。
タイトル:「子どもをささえる絵本の力」
話者:一戸 盟子さん(福音館書店月刊誌編集部長)
お話しの中で印象的だったのは、この9月に出版された絵本(2才~)「ケーキ(小西英子作)」の
制作についての解説でした。
絵本作家の小西さんはこの絵本を描くにあたって、何度も何度もケーキをつくったそうです。
リンク先(下記)の画を見ていただけるとわかりますが、つくる工程やスポンジの断面、ホイップクリームの色、
デコレーションのフルーツのセレクトに至るまで、自身で作ったからこその臨場感があります。
そして、絵本のページをめくった時に、子どもの眼にその絵がどのように映るのか、
本当にこの画角でいいのか、編集者の一戸さんと作家の小西さんは
まさに子どもの気持ちになって幾度も描き直しながら検討したそうです。
その結果、ケーキが出来上がるまでの過程をシンプルに描いたその絵本は
「次はどうなるのだろう?」とページをめくりたくなる衝動と
「本物を見てみたい」「食べてみたい」「作ってみたい」という目標を
子どもに提供しているのだということが分かります。
絵本制作は「子どものこころ、大人の目」が大切だと、一戸さんはお話しされていました。
これは絵本に関わらず、子どもが触れるコンテンツのすべてに通じるのではないでしょうか。
そして、「絵本を読んだ感想を子どもに求めない」とも。
感想を聞いた瞬間に、子どもは「絵本を読むと感想を言わなければならない」
となってしまうからだそうです。
なにを読みたいか、を 子どもに任せ、どう感じるか、も 子どもに任せ、
それを表現するかどうか、 も任せる。
絵本は子どもにとって安心して出かけられる
「自由な冒険の空間」なのだと、私は理解しました。
最後に一戸さんのスライドにあった言葉を引用します。
“石井桃子(※)さんの言葉
『大人になってから
老人になってから
あなたを支えてくれるのは
子ども時代のあなたです』”
※石井桃子:(いしい ももこ、1907年3月10日- 2008年4月2日)は、日本の児童文学作家
文中の絵本紹介:「ケーキ(小西英子作)」https://www.fukuinkan.co.jp/book/?id=7597
日本子ども学会リンク:https://kodomogakkai.jp/

こんにちは。歯科衛生士・こども成育インストラクターの宗田香織です。
前回に引き続き、ユニバーサルデザインフードセミナーのレポートを交えながら
乳幼児の咀嚼嚥下機能の発達や、ユニバーサルデザインフードの活用法などを
考えてみたいと思います。
咀嚼嚥下の機能に合わせた食事の楽しみ方 :ユニバーサルデザインフードセミナーレポート〈前編〉
生まれたばかりの乳児の栄養摂取は、母乳や人工乳などの液体から始まり、
離乳食では歯の萌出に合わせて様々な食材を初めて食べます。
何度も食べる訓練を重ねながら、だんだんと大人と同じ食べ物が食べられるようになっていきます。
口腔機能が目まぐるしく発達する時期ですが、それに伴い口腔内の変化も大きい時期です。
歯が生える時は痛みや違和感がある上に、どんな風に唇や舌を動かしたら
初めて食べる物を上手く噛めるか?どうやって噛んだら痛くないか?など
身体が慣れていないので、怖さも感じながら食事をしています。
私たち大人も乳児期に経験してきたのですが、その時期を過ぎるとすっかり忘れてしまいます。
咀嚼嚥下が当たり前にできているからこそ、乳歯から永久歯への生え変わりの時期や
歯科治療中、口内炎ができた時などに不快な思いや痛みを感じると
咀嚼嚥下機能が低下するので困惑することもあります。
いつもは当たり前に食べていた物が食べられない
好物や美味しく感じていた物でも食べたくない
そもそも食欲が湧かない
など食事に支障をきたし、一時的ではあるもののQOLもガクッと下がります。
もしかすると、精神的なショックは、大人になってからこの体験をした時の方が
大きく感じるかも知れません。
「口内炎ができて、水もしみる… これがいつまで続くんだろう」
「親知らずを抜いたら腫れて1週間以上何も食べられなかった…」
という経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そういった時は、無理していつもの食事をするのではなくユニバーサルデザインフードに
頼ってみると栄養素もしっかり摂れ、治癒促進にも繋がることでしょう。
歯科医院では、保護者の方から乳幼児だけではなく小学生〜高校生と
幅広い年齢のお子さんの食事についての相談を受けることもあります。
・好き嫌いが多い
・甘い物や柔らかいものしか食べない
・ちゃんと噛まない
は、どの年齢でもよく相談内容として挙がります。
おとなの視点では、単なる「子どものわがまま」と捉えがちです。
しかしながら子どもの視点では、口腔の状態やそれに伴う機能低下、痛みなどが原因で
食べたくても食べられずに困っていたということは少なくありません。
そんな時も、歯科衛生士などに相談して一時的にユニバーサルデザインフードを活用したり、
それを目安にお子さんが食べられる食材の固さや大きさなどをご家庭で試してみたりすることもおすすめです。
今回のセミナーを受けて、ユニバーサルデザインフードは咀嚼嚥下機能に段階的に合わせた形状だけでなく
栄養バランス・色彩においても工夫をなされていることを知りました。
また、状況に合わせて選択肢も多いことから、患者様を支える上で歯科衛生士の
心強いアイテムになるとも感じました。
セミナーでは試食もさせていただきました。
いざその時になって初めて食べさせる(食べる)のではなく
提供・介助する側も食べてみて味や食感を共有することも大切です。
離乳食の疑似体験をしてみると、お子さんの口腔や咀嚼嚥下機能の成長発達を知る上で
大人にとっても良い経験になるのではないかなと思います。
今回の体験を通じて、心身共に健康を支える普段の食卓において
誰もが幸せに感じられるよう商品開発に真摯に取り組んでいるキユーピー株式会社様の
企業努力を知ることができました。
最後になりましたが、キューピー株式会社 前田様・山田様にこの場をお借りして
御礼申し上げます。

宗田 香織
1996年 東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校を卒業後一般歯科や審美・矯正歯科などにて勤務。
2000年 Dr岡本・Dr竹内よりスウェーデン歯周病学を学び、歯周治療・メンテナンス・
インプラント予防管理を中心に歯科クリニックに勤務。
2018年10月よりこども成育インストラクター〈食専科〉アンバサダーとしても活動中。

こんにちは。歯科衛生士・こども成育インストラクターの宗田香織です。
気温が低い日が続くようになり秋の気配を感じるようになりました。
皆さんは〇〇の秋、と言うとどんな言葉を思い浮かべますか?
私はやはり“食欲の秋”。
それぞれの季節の旬のものは一年を通じて食卓の楽しみになっていますが、
秋の食材はなにか特別です。
ということで、今回のブログではいつもと少し目線を変えて、
大人の食事から乳幼児の咀嚼嚥下機能の発達を考えてみようと思います。
先日、日本こども成育協会にて開催したユニバーサルデザインフードセミナーの
レポートも交えてお届けします。
ユニバーサルデザインフードとは?
皆さんは、「ユニバーサルデザインフード」という言葉を聞いたことがありますか?
「介護食」という方が、耳なじみがあるかも知れません。
介護食というと、高齢になって歯が悪くなったり、入れ歯になったりしたら
食べる物というイメージがあるかと思います。
一方でユニバーサルデザインフードは、年齢や障害のあるなしに関わらず
咀嚼嚥下機能に応じた日常の食事から介護食まで、できるだけ多くの人が
利用できるように考えられた『食べやすさに配慮したやさしい食品』のことです(※1)。
また、ベビーフードとの違いは
味が濃い、栄養素が多い、塩分が高い(UDF2%⇔ベビーフード0.5%)ということがあげられます。
※ユニバーサルデザインフードは、乳幼児には与えないように注意が必要です。
私は、幼少期に祖父母・曾祖母と一緒に過ごすことが長く、同居人数も多かったので
介護食や離乳食を含めた各世代別の献立が並ぶ食卓の風景は身近でした。
「おじいちゃん・おばあちゃんになると食べられないものが増えて
いつも柔らかいものばかりだし、食べるのも大変そうだな…美味しいのかな?」
「様々な料理を作るお母さんも大変だな」
と子どもながらに感じていましたが、自分が介護食を食べるのはずっと先のことだと思っていました。
料理が好きで、中学高校生の頃になると祖父母に何か作ることも増え、
自分なりに咀嚼嚥下に配慮した調理もしていました。
これまで自分流に作っていたので、歯科医院でも活かせる介護食を…と調べていたところ
ユニバーサルデザインフードの取り組みについて知る機会があったのです。
高齢者だけではなく、例えば歯の生え替わりの時期の子どもたちや、
矯正治療中・抜歯などの術後などにも活用できるのではないかと感じました。
そこで、キユーピー株式会社様にて行われたユニバーサルデザインフードのセミナーを
7月に受講し、これは日本こども成育協会の活動でも活かせそうと思い、
改めてセミナーを協会にて開催していただきました。
ユニバーサルデザインフードは咀嚼機能に応じ4段階に分けて作られています。
キユーピーの特設サイト(※2)に掲載されている簡単なチェック項目で、
どの段階の食品が合っているかがわかるので、対応したものを商品ラインナップから選ぶことができます。
先に述べたように、高齢になった時だけではなく
・むし歯などの治療中や術後
・矯正治療中で歯に負担がかかって痛みがある時
・口内炎や傷がある
・歯の生え変わりの時期
などの時期は、咀嚼嚥下(噛む・飲み込む)機能が普段と比べると低下します。
またよく嚙めないことで味覚にも影響が出るので、食事が美味しいと感じられなくなってしまいます。
いつもの食事をいつも通り良く噛んで味わい楽しんで食事をすることが想像以上に困難になりますが
こういった商品を取り入れることで、いつでも誰でも安心して食べられます。
また、提供・介助する側の負担も少なく活用できると感じました。
次回に続く。
※1 参考サイト:ユニバーサルデザインフード 日本介護食品協議会 (udf.jp)
※2 やさしい献立 キユーピー株式会社
https://www.kewpie.co.jp/udfood/
********************************************
宗田香織さんが講師を務める「うちの子専属トレーナー」資格 10&11月受講申込受付中です!
◆10月受講申し込みページ
https://uchinoko2410.peatix.com
◆11月受講申し込みページ
https://uchinoko2411.peatix.com
********************************************

宗田 香織
1996年 東京都歯科医師会附属歯科衛生士専門学校を卒業後一般歯科や審美・矯正歯科などにて勤務。
2000年 Dr岡本・Dr竹内よりスウェーデン歯周病学を学び、歯周治療・メンテナンス・
インプラント予防管理を中心に歯科クリニックに勤務。
2018年10月よりこども成育インストラクター〈食専科〉アンバサダーとしても活動中。

クラウドファンディング CAMPFIRE for social goodで183%を達成し
今秋より満を持して開講したパパ待望の子育てスキル講座『うちの子専属トレーナー』。
前回は、選択科目の一つ「うちの子専属「ワイルドベビー」トレーナー認定講座」の
講義前半「0歳児からできる!リンパアクティベーション」についてご紹介しました。
パパ大活躍!簡単なストレッチで元気な赤ちゃんに★うちの子専属「ワイルドベビー」トレーナー認定講座
今回は、後半部分となる「おうちの中にあるもので運動神経ステップアップ」についてお伝えします!
講師は同じく、フィジカルトレーナーであり、ベビーリンパアクティベーション協会顧問の櫻井優司先生です。
前半は0歳児のベビーからでもできる内容でしたが、後半は1~2歳ぐらいのお子さんを主な対象としています。
「おうちの中にあるもの」と謳っているように、使うのはタオルや新聞紙、ティッシュペーパーなど。
タオルを引っ張ったり、新聞紙をちぎったり、ティッシュペーパーを口で吹くことで鍛えられ、刺激される筋肉や感覚、
機能について櫻井先生が解説します。
いずれも難しい動きではなく、お子さんによっては自然とそうした遊びをしている場合もあるかもしれません。
たとえば、新聞紙をビリビリ破いて遊んでいたらどうでしょう?
「もうゴミばっかり増やして!」と思ってしまうかもしれませんが、櫻井先生の解説を聞いた後なら、
「手先が器用になっているね」と笑顔で見守れるようになるはずです。
こうした「いたずら」をしながら、皮膚感覚や脳の発達などを促すのが「ワイルドベビー」流のトレーニングなのです。
また、お子さん一人で遊ぶのではなく、パパ(もちろんママも!)も一緒に楽しく遊べることもポイントです。
動画に登場してくださった親子も、最初は緊張していたお子さんが、パパが笑顔で楽しそうにやっているのを真似しているうちに
ニコニコ顔になっていくところも必見です!
このように、雨の日はおうちのなかで、晴れて気持ちの良い日は公園などで、特別な物を用意しなくても
楽しくコミュニケーションを図りながら、お子さんの成長や発達を見守ることができるヒントが
いっぱい詰まっている講座内容となっています。
このほかにも、『うちの子専属トレーナー』には、はみがき好きに育む「はみがきトレーナー」認定講座もご用意しています。
こちらの講師は、歯科衛生士で本ブログでもおなじみの宗田香織さんです。
講座内容についても今後ご紹介していきますのでお楽しみに!
********************************************
「うちの子専属トレーナー」資格 10月受講申込受付中です!
◆10月受講申し込みページ
https://uchinoko2410.peatix.com
◆11月受講申し込みページ
https://uchinoko2411.peatix.com/
********************************************

こどもの心理発達と行動を7つの領域から観察することで、それぞろえの領域で「今できていること」と「これからできること」を見つけ、こどもの状や胃や個性に合わせた適切なコミュニケーションを生み出すことができます。
この講座では「こどもの今」を多角的に観察するためのアプローチをお伝えします。